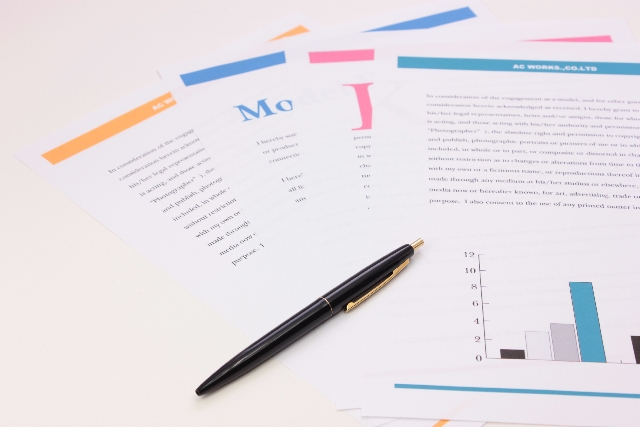


先ほど失業保険の事でお伺いしたんですが、
健康保険は失業保険中、受給期間中のパートを(申告して)していても主人の扶養にはいれるのでしょうか?
知ってたら教えて下さい
健康保険は失業保険中、受給期間中のパートを(申告して)していても主人の扶養にはいれるのでしょうか?
知ってたら教えて下さい
雇用保険を受給中の方が健康保険の被扶養者になれるのは、受給できる基本手当日額(失業等給付の日額)が一般的に3,612円未満であることが必要です。これは健康保険の扶養になる要件のひとつとして、今後1年間の収入の見込み額が130万円未満であることが必要であり、この3,612円未満という額は130万円を360日で割った金額から求められます。
あなたの基本手当日額+パート日額<3612円ならば 扶養になれるでしょう。
あなたの基本手当日額+パート日額<3612円ならば 扶養になれるでしょう。
健康保険の扶養家族
事情があって会社を退社後、次の再就職先が決まるまでいつになるか
判らない為、一時的に親の扶養で再加入したいと思うのですがこういう
場合どのような手続きが必要で再加入までどれくらい時間がかかるものですか?
退社時点での今年度通算収入は僅かですが失業保険を含めると
130万を超えると思いますがこの場合は来年の申請になるのでしょうか?
ご存知の方宜しくご教授下さい
事情があって会社を退社後、次の再就職先が決まるまでいつになるか
判らない為、一時的に親の扶養で再加入したいと思うのですがこういう
場合どのような手続きが必要で再加入までどれくらい時間がかかるものですか?
退社時点での今年度通算収入は僅かですが失業保険を含めると
130万を超えると思いますがこの場合は来年の申請になるのでしょうか?
ご存知の方宜しくご教授下さい
失業手当の日額(基本手当日額)が3612円以上だと健康保険の被扶養者になれません(60歳以上と障害者は別基準)
3611円までなら退職日の翌日から被扶養者になりますが
申請が遅れるとさかのぼっては被扶養者にならないかもしれません
あと、保険証が実際に手元にくるのは申請してから2週間~1ヶ月ぐらいかかります
添付書類が指示されますので、健保に提出してみてください
細かい条件とか金額とかわからないとどっちとも言えませんので
親と同居してます?
3611円までなら退職日の翌日から被扶養者になりますが
申請が遅れるとさかのぼっては被扶養者にならないかもしれません
あと、保険証が実際に手元にくるのは申請してから2週間~1ヶ月ぐらいかかります
添付書類が指示されますので、健保に提出してみてください
細かい条件とか金額とかわからないとどっちとも言えませんので
親と同居してます?
確定申告について。
知恵をお借りしたいです。
私は本年度4月まで、正社員としてA社に勤務しておりました。退職後、A社より源泉徴収表を貰い、その後に職業訓練所に行き、失業保険を頂きなが
ら、10月にB社に就職しました。しかし、二週間程で退職後しました。B社に就職する時に、A社で貰った源泉徴収表を渡しました。そしてB社退職後はB社の源泉徴収表を頂きました。今年の就職は厳しいので、自分で確定申告をしないといけないと思っています。
そこで質問なのですが、
1、確定申告の際に、A社の源泉徴収表は再度A社に頂かないといけないのでしょうか?
2、A社退職後は、市県民税は本年度は一括で支払いましたが、国民年金は5月から未払い。社会保険は喪失の手続きをしておらず、5月から、保険証がない状態です。
A社在職中の本年度2月に保険対象外でレーシックに17万程かかり、
4月には、保険対象で三割負担で7000円程歯科に通いました。
また今月、産婦人科に通い、経済的な理由により、自費で中絶手術と前後の費用14万ほど使いました。
確定申告の際にこれらは、
申告する事により、還付はうけられるのでしょうか?
A社の源泉徴収表はB社に提出してしまったため手元にはないのですが、給料明細がありましたので、
みると、A社の最後に貰った明細には
総支給額累計1130659
非課税手当累計24600
源泉対象支給額累計1106059
社会保険料累計138892
源泉所得税累計22180
と書いてありました。
B社は二週間での退社なので、手元にあるB社の源泉徴収表は
支払い金額60681
源泉徴収税額0となっています。
知恵をお借りしたいです。
私は本年度4月まで、正社員としてA社に勤務しておりました。退職後、A社より源泉徴収表を貰い、その後に職業訓練所に行き、失業保険を頂きなが
ら、10月にB社に就職しました。しかし、二週間程で退職後しました。B社に就職する時に、A社で貰った源泉徴収表を渡しました。そしてB社退職後はB社の源泉徴収表を頂きました。今年の就職は厳しいので、自分で確定申告をしないといけないと思っています。
そこで質問なのですが、
1、確定申告の際に、A社の源泉徴収表は再度A社に頂かないといけないのでしょうか?
2、A社退職後は、市県民税は本年度は一括で支払いましたが、国民年金は5月から未払い。社会保険は喪失の手続きをしておらず、5月から、保険証がない状態です。
A社在職中の本年度2月に保険対象外でレーシックに17万程かかり、
4月には、保険対象で三割負担で7000円程歯科に通いました。
また今月、産婦人科に通い、経済的な理由により、自費で中絶手術と前後の費用14万ほど使いました。
確定申告の際にこれらは、
申告する事により、還付はうけられるのでしょうか?
A社の源泉徴収表はB社に提出してしまったため手元にはないのですが、給料明細がありましたので、
みると、A社の最後に貰った明細には
総支給額累計1130659
非課税手当累計24600
源泉対象支給額累計1106059
社会保険料累計138892
源泉所得税累計22180
と書いてありました。
B社は二週間での退社なので、手元にあるB社の源泉徴収表は
支払い金額60681
源泉徴収税額0となっています。
A社の源泉徴収票がないと、還付は絶対にされない。
よってこれをA社に言って再発行をさせるか、B社で返還してもらいましょう。
確定申告をすれば所得税の全額が22180円が帰ってきます。
よってこれをA社に言って再発行をさせるか、B社で返還してもらいましょう。
確定申告をすれば所得税の全額が22180円が帰ってきます。
Q1: 扶養の範囲内の103万、130万の年収とは いつからいつまでの収入で計算するんですか?
(働いた期間ではなく給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?)
私の場合ですが、4月末のお給料が最後でした。ということは、1月末~4月末払いが年収対象ということでいいのでしょうか?
Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
無職の間の、5月~10月まではダンナの扶養に入れてもらってたので 市民税は払いましたが
国民健康保険と国民年金はダンナの給料から引かれていました。(仕事していた時は自分のお給料から保険・年金は
支払ってました)
再就職が決まり(とはいえ、11月と12月の短期派遣で、それが終われば再度 無職です)
Q3: もし ここで 103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか?
103万超えになるかは今時点では分からないので 後で(年明け)の申告でも
大丈夫なのでしょうか?
Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
長々と 質問してスミマセン。 無知なもので教えてください。
(働いた期間ではなく給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?)
私の場合ですが、4月末のお給料が最後でした。ということは、1月末~4月末払いが年収対象ということでいいのでしょうか?
Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
無職の間の、5月~10月まではダンナの扶養に入れてもらってたので 市民税は払いましたが
国民健康保険と国民年金はダンナの給料から引かれていました。(仕事していた時は自分のお給料から保険・年金は
支払ってました)
再就職が決まり(とはいえ、11月と12月の短期派遣で、それが終われば再度 無職です)
Q3: もし ここで 103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか?
103万超えになるかは今時点では分からないので 後で(年明け)の申告でも
大丈夫なのでしょうか?
Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
長々と 質問してスミマセン。 無知なもので教えてください。
1A:「103万円以下」とは、あなたを扶養している人が受ける「配偶者控除」の収入限度額を指します。
その年の1/1~12/31が対象となります。「130万円未満」とは、健康保険の被扶養者としての収入における資格要件です。この場合の期間は、被扶養者となる時点において「その後の1年間」を指します。月額換算108,333円以下(108333×12ヶ月=130万円未満)であれば被扶養者資格を有することになります。
2A:所得税については含めませんが健康保険では含めます。
3A:「見込みの額」で申告してください。
4A:「扶養手当」「家族手当」等と称し、規定は事業所が任意で設定いたします。一般的には「控除対象配偶者」または「扶養親族」の要件である「年間収入103万円以下の者」とすることが多いうようです。
その年の1/1~12/31が対象となります。「130万円未満」とは、健康保険の被扶養者としての収入における資格要件です。この場合の期間は、被扶養者となる時点において「その後の1年間」を指します。月額換算108,333円以下(108333×12ヶ月=130万円未満)であれば被扶養者資格を有することになります。
2A:所得税については含めませんが健康保険では含めます。
3A:「見込みの額」で申告してください。
4A:「扶養手当」「家族手当」等と称し、規定は事業所が任意で設定いたします。一般的には「控除対象配偶者」または「扶養親族」の要件である「年間収入103万円以下の者」とすることが多いうようです。
関連する情報